【SNS疲れ対策】心がすり減らない距離感の作り方
こんにちは。「LIFE LAB 人生を豊かにする人生の研究室」へようこそ。DAI研究員です!!
いきなりですが、あなたはSNSで疲れていませんか?
便利で楽しいはずのSNS。
でも、「他人の投稿を見るとモヤモヤする」「通知が気になって集中できない」「誰かの評価が気になる」と感じている人は少なくありません。
この記事では、SNS疲れの原因と対処法、そして心がすり減らないSNSとの距離感の作り方について解説します。
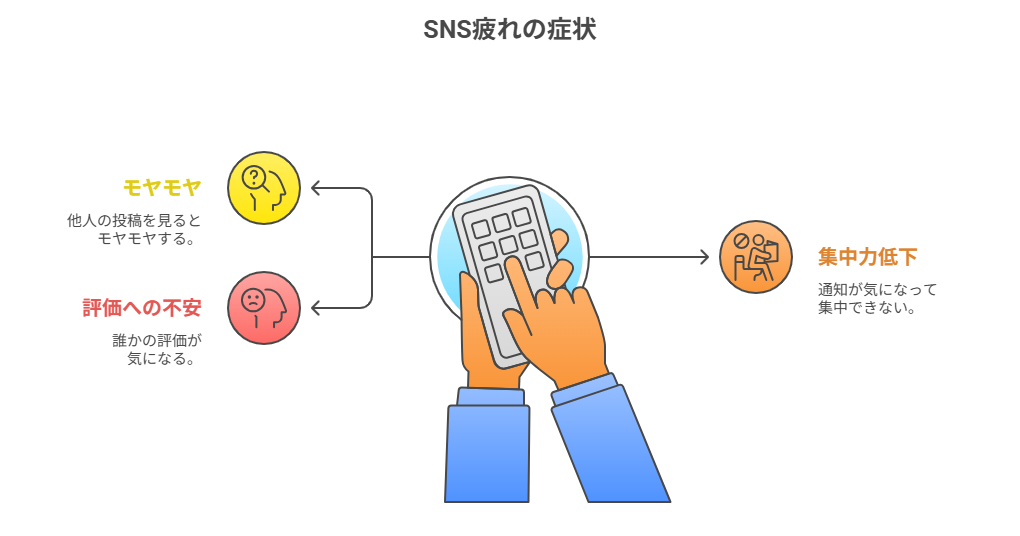
SNS疲れとは?
SNS疲れとは、SNSを利用することで、心や思考に疲労やストレスを感じる状態のことです。
楽しさやつながりを感じられる一方で、以下のような状態が積み重なることで「SNS疲れ」に陥ってしまいます
- 人の投稿と自分を比べて落ち込む
- 常に通知が気になってしまう
- 返信や「いいね」を義務のように感じる
- 炎上やコメントに敏感になってしまう
気づかないうちに、SNSは「人とのつながりのため」から「人に気を遣う場所」へと変わってしまっているのです。
SNS疲れを感じやすい人の特徴
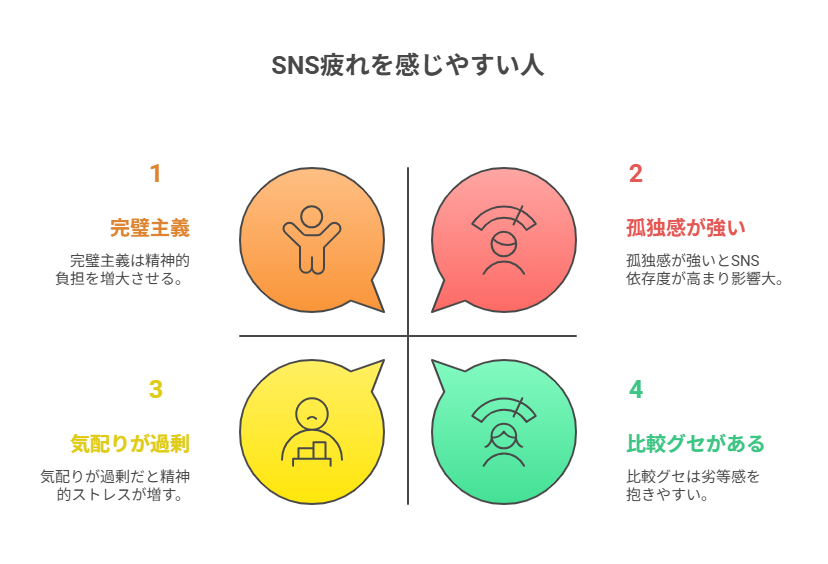
- 完璧主義:投稿の反応や見た目に敏感で、常に「もっと良く見せなきゃ」と感じてしまう。
- 比較グセがある:他人の生活・実績・写真と自分を比べてしまい、劣等感を抱きやすい。
- 気配りが過剰:既読スルーや返信の遅れに罪悪感を抱いてしまう。
- 孤独感が強い:SNSだけが人とつながる手段になっており、距離を取ることが怖い。
こうした傾向がある人は、意識的に「SNSとの距離感」を見直すことが大切です。
SNS疲れチェックリスト あなたはいくつ当てはまる?
SNSに疲れているかも…と思ったら、まずは自分の状態をチェックしてみましょう。
以下の10項目のうち、いくつYESがあるかを数えてみてください。
- ① SNSを開くのが習慣化していて、時間を忘れて見てしまう
- ② 他人の投稿を見て、無意識に自分と比較して落ち込む
- ③ 「いいね」やコメントが少ないと不安になる
- ④ 自分の投稿に対して、過剰にリアクションを気にする
- ⑤ 誰かのストーリーや投稿を見ないと取り残される気がする
- ⑥ 通知が鳴るとすぐにスマホを開いてしまう
- ⑦ SNSを見たあと、なぜか心がザワザワすることがある
- ⑧ 見たくない内容でも惰性で見続けてしまう
- ⑨ SNSを見たあと、無力感・焦燥感を覚えることがある
- ⑩ SNSをやめたいと思いつつ、やめられない
【判定結果】
- YES 0〜2個 → 今のところは健全な付き合い方ができています。
- YES 3〜5個 → 少しSNSとの距離感に注意。使い方を見直すタイミングかもしれません。
- YES 6個以上 → SNS疲れが進行中。対処や距離の取り方を本格的に考えてみましょう。
YESの数が多いほど、心の奥でSNSとの関係にストレスを抱えている可能性が高いです。
気づいたときが、改善のチャンスです。
次に紹介する「心がすり減らないSNSとの距離感の作り方」もあわせて参考にしてみてください。
心がすり減らないSNSとの距離感の作り方
SNSとの“適切な距離”をつくるには、単に「見ないようにする」だけでなく、自分にとってのSNSの役割を明確にし、習慣そのものを見直すことが大切です。
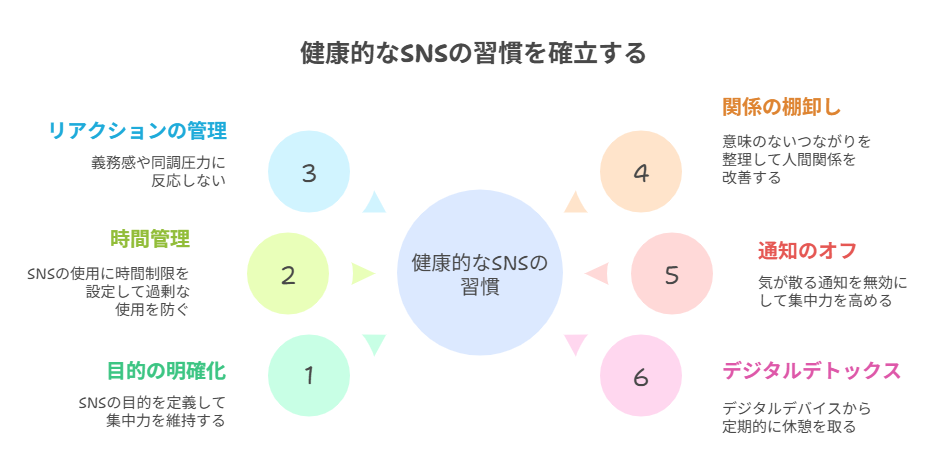
① SNSを使う「目的」を明確にする
人によって、SNSを使う理由は違います。
- 情報収集したい(ニュース、学び)
- 誰かとつながっていたい
- 自己表現したい(作品・言葉)
- ビジネスや副業のため
この「目的」を忘れたまま使い続けると、依存や疲労につながります。
おすすめアクション:
ノートやスマホのメモに「自分がSNSを使う目的」を書き出してみましょう。
明文化するだけで、行動がブレにくくなります。
②「SNSを見る時間」と「見ない時間」を決める
SNS疲れの多くは「ダラダラ見る習慣」が原因です。見る時間を意識せずに使うと、脳の情報処理が追いつかず、疲労が蓄積されてしまいます。
改善例:
- 朝:ニュースチェックだけ10分
- 昼:昼休みに10分スクロール
- 夜:21時以降はスマホオフ
アプリの使用時間制限や“おやすみモード”を活用して、「時間で線を引く」ことがコツです。
③「リアクション疲れ」を防ぐ
いいね返し、コメント返し、既読無視の罪悪感…SNSは気づかぬうちに「義務感」や「同調圧力」を生みます。
ですが、すべての投稿に反応しなくてもいいのです。
自分のリズムで関わることが、心を守る距離感の基本です。
おすすめフレーズ(コメント不要の投稿に):
「読んでくれてるだけでうれしいよ😊」と事前に書いておくと、お互いに気がラクになります。
④ フォロー/フォロワーは「人間関係の棚卸し」
リアルでは関係がないのに、惰性でつながっているアカウントはありませんか?
SNSのフォローは「人間関係の距離感」を象徴します。
違和感を覚える相手は“静かに離れる”選択をしてOKです。
やさしい方法:ミュートやストーリー非表示を使えば、関係を壊さずに距離を取れます。
⑤ SNSの「通知」は全部オフでOK
通知音やバッジは、脳にとって「やらなきゃ」「見なきゃ」と焦りを生む刺激です。
多くのSNS依存は「通知が来る→すぐ開く→また見てしまう」のループから始まります。
通知を切ることで、このループを止められます。
おすすめ設定:スマホの「通知設定」から、SNSアプリの通知をすべてOFFに。
⑥「スマホを置く時間」を毎日つくる
スマホ=SNSではありませんが、現代人の習慣的な入口になっているのは事実です。
だからこそ、1日30分でも「スマホを見ない時間」を作ることで、心が整います。
おすすめ習慣:
- お風呂中はスマホ持ち込み禁止
- 朝起きてから30分はスマホを見ない
- 寝る前1時間はスマホオフ+読書や音楽に
この「デジタルデトックス時間」は、自分の心の声と向き合える貴重な時間になります。
まとめ
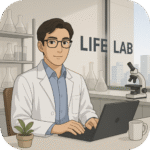
SNSは「付き合い方」がすべてです。
便利なツールであると同時に、心を疲れさせるリスクもあります。
大切なのは、SNSを「やめる」ことではなく、「どう付き合うか」を考えること。
通知を切る・見る時間を決める・ミュートを使うなど、自分の心を守るための習慣を取り入れていきましょう。
「疲れた」と感じたら、それは心のサインです。
自分を責めずに、少し距離を置いてみること。
それが、SNSとうまく付き合う第一歩です。
上手に使えば非常に便利なものですので、良い付き合い方が出来るように一緒に頑張りましょう!!



コメント